微生物が紡ぐストーリー(食と健康学類 応用微生物学研究室 山口昭弘教授・村松圭准教授)
食と健康学類応用微生物学研究室(山口昭弘教授・村松圭准教授)では、有用微生物の探索や新規発酵食材の開発に関する基礎研究を行っている。発酵食品を支える酵母や乳酸菌など有用な微生物の力を借り、健康増進作用が注目されるものの食味に難点がある道産機能性食材のアロニア、シーベリー、赤ビートなどを美味しくし、機能性を向上させる研究や、アカエゾマツ精油・蒸留残液などの天然素材が持つ抗菌・防虫作用を探る。
応用微生物学研究室を特徴付ける活動の一つがワインサークルROWP(酪農学園大学オリジナルワインプロジェクト)だ。2015年に酒類の試験醸造免許の交付を受け、野生酵母の探索・発酵特性に関する研究を行っている。2016年には学内のブドウ(キャンベル・アーリー)を使用したオリジナルワインを包括連携協定先の北海道ワイン株式会社(小樽市)から発売。2018年からは、同大学OBが所有する砂川・ROWP豊沼ヴィンヤードのソービニヨン・ブラン2,500本の苗管理を含め、ブドウ栽培、ワイン醸造、ラベルデザインから製品化まで一連のワインづくりに携わり、ものづくりの楽しさを学ぶ全学的な学生団体「ワインサークルROWP」として幅広い活動を行っている。
ROWPの活動と並行して同研究室では、新たな原料によるワインづくりの研究が進められた。2020年6月には、社会人大学院生で大学院酪農学研究科食品栄養科学専攻修士課程の南典子さんが「赤ビートワイン」を完成させた。その前年には赤ビートワインの発酵条件をテーマに学会で発表。「学内野生酵母の分離と赤ビートワイン醸造への応用」を研究テーマとし、学内のシーベリーから分離した野生酵母を用い、赤ビート原料を合同会社アグマリンプロテック社(江別市)から無償提供を受け、委託醸造先としてばんけい峠のワイナリー(札幌市)の協力を得て、世界初となる赤ビートワイン(ハーフボトル360ml・80本)を完成させた。
また、2021年3月には、大学院修士課程1年の前野奈緒子さんが「はすかっぷクルゼイワイン」を完成。前野さんは、地元食材を活用した付加価値を高める商品開発を目標として「ハスカップの果皮(搾汁残渣)を用いたワイン醸造と製品開発」をテーマに研究。ハスカップは苫小牧市勇払原野の自生する小果樹で、北海道を代表する抗酸化機能食品として注目を集めている。しかし、元々収穫量が少なく、果実は傷みやすいため、生果実としての流通は初夏の極めて短い一時期だけ。多くは冷凍果実や果汁として、大半が菓子などに利用されている。搾汁後の残渣にもアントシアニンが多く含まれているにもかかわらず、ほとんど有効利用されていないのが現状だ。
前野さんは有限会社はすかっぷサービス(苫小牧)より提供された、ハスカップの搾汁残渣である果皮にハスカップ果実から分離した酵母カンディダ・クルゼイを加え、ばんけい峠のワイナリーに醸造を委託。アルコール度数7%と9%の2種類を試作し、官能検査などの結果、9%のワインを商品化し販売することになった。
一方、ワイン以外の酒の製品化にも取り組んでいる。その一つがホエイ酒だ。チーズを作る際に副産物として発生するホエイ(乳清)は、栄養価が高いことから一部は粉末化して家畜の飼料やプロテインに加工されているが、加工コストが課題となり、多くは廃棄されている。ホエイ酒は、チーズホエイから分離した野生酵母と麹でホエイを発酵させたもので、爽やかなお酒に仕上がるという。ホエイを加工して酒に用いた研究事例はあるが、生タイプのホエイそのものを活用して製品化した前例はなく、世界初の研究と言える。研究は今春卒業した亀田くるみさんが卒業論文にまとめ、共同で研究・開発を進めた田中酒造株式会社(小樽市)が製品化する。
同研究室では、KONDOヴィンヤード(岩見沢市)のクヴェヴリ・ワインの発酵メカニズムの解明に取り組んでいる。クヴェヴリ・ワインは東欧ジョージアの伝統ワインで、大人が入れるほどの大きさの素焼きの発酵容器を土に埋め、そこにブドウを入れて半年~1年放置してできる自然発酵ワイン。KONDOヴィンヤードでは、ジョージアから発酵容器を輸入し、クヴェヴリ・ワインを生産している。同研究ではヴィンヤード環境に順応した野生酵母を分離・培養し、ブドウの苗や果実に高密度で着生させることにより、微生物農薬として病原菌の増殖を抑制、アルコール発酵速度を高めることで、より安全な自然発酵ワインの醸造実現を目指している。 このほか、アカエゾマツ精油の抗菌性・抗炎症作用、胃がんの原因とされるピロリ菌の抗菌性、トマト麴のメラニン抑制作用、クロカワというキノコの機能性など、学内・道内で取れる微生物の機能性を探索し、道産食材の機能性向上や食味の改善に役立てている。

山口教授は、
「有用な酵母や乳酸菌などの微生物を見つけ、道産素材と組み合わせることで、機能性を高め、あるいはより美味しい食材を開発しています。外部の菌ライブラリーに頼るのではなく、身近なところにある数百種類の野生の菌株から有用なものを見つけ、道産食材と組み合わせることで、そこに生まれるストーリー性を大事にしています」
と語る。学生の夢や興味を尊重し、自分で考え、動ける学生の育成を目指している。
今年度のゼミ生は、3年生・4年生がそれぞれ13~14人と院生を合わせて約30人。卒業生の就職先としては、道内外の食品会社の品質管理部門が多い。なお、同研究室は2023年4月から発酵科学ユニットに衣替えする予定だ。
(月刊ISM 2021年11月号掲載)

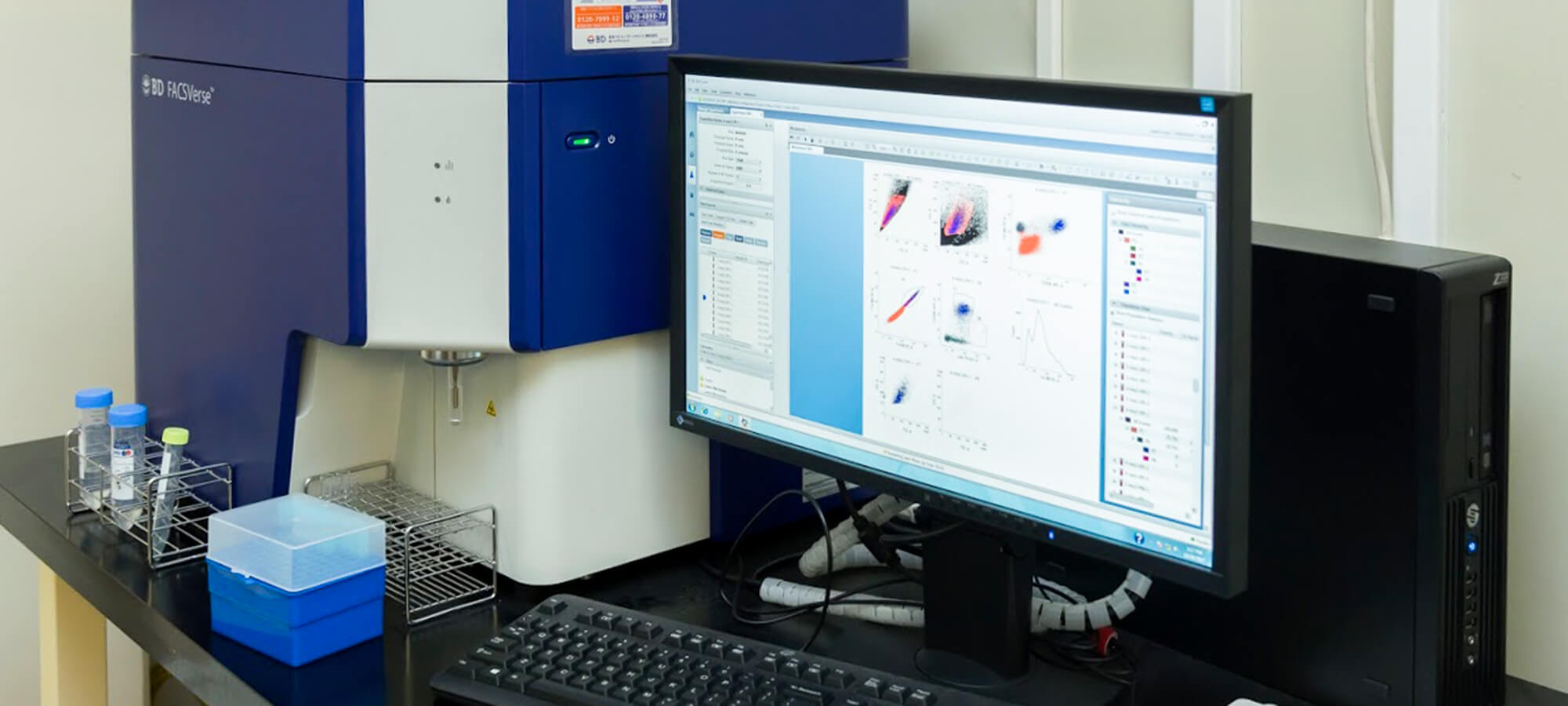
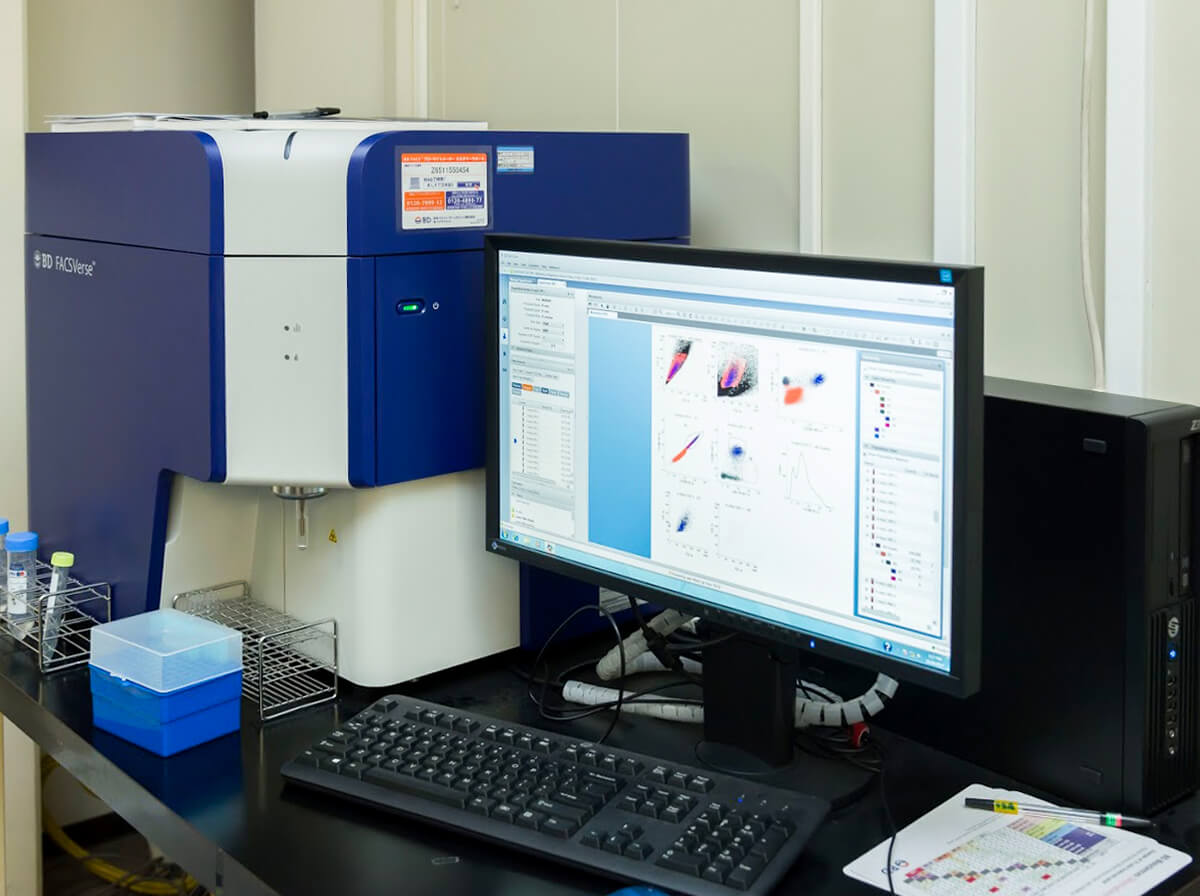


 資料請求
資料請求 受験生サイト
受験生サイト