効率的な葯培養法の技術(循環農学類 植物育種学研究室 岡本 吉弘 准教授)
農食環境学群循環農学類植物育種学研究室(岡本吉弘准教授)では、「水稲における飛躍的に高い葯(やく)培養法の開発~いかにして多数の花粉から多数の植物体を作るか」をテーマに研究を進めている。従来の交雑育種法では遺伝子を固定するために自殖を10回繰り返す必要があるのに対し、葯培養法では、たった1回の培養で遺伝子を固定できるのが特徴。植物育種学研究室では、より高効率な葯培養技術の開発に取り組んでいる。
かつて“ヤッカイドウ米”と呼ばれるほど食味に劣っていた北海道米。1980年から北海道では、道立農業試験場(現道総研)を中心に水稲育種プロジェクトチームが発足。食味の良い新品種育種に取り組んだ。87年に「上育394号」、88年に「きらら397」、92年に「彩」、2001年に「ななつぼし」、03年に「ふっくりんこ」、08年に「ゆめぴりか」を世に出した。中でも「ななつぼし」と「ゆめぴりか」の良食味性は、道内外に広く知られ、今では水稲作付面積の約半分を「ななつぼし」、約4分の1を「ゆめぴりか」が占める主力品種に育っている。
イネの葯培養による半数体の作出と二倍体植物の遺伝的固定が可能であることは1968年、71年に日本人の研究者(新関宏夫、大野清春)が世界に先駆けて示した。国内では従来の交雑育種法により良食味品種が開発されていたことから普及しなかったが、北海道の水稲育種プロジェクトチームは、1回の培養で遺伝子固定が可能な点に着目し、葯培養法を使った新品種育種に取り組んだ。前述の「上育394号」は日本で初めての葯培養品種であり、「彩」「ななつぼし」「ゆめぴりか」の育種にも葯培養法が用いられているのだ。
葯培養法は、葯(おしべの先端にある花粉が詰まった袋)を培地上で培養し、植物体に育てる方法。葯を培養すると、カルスという細胞の塊ができ
る。カルスを別の培地で培養すると、万能細胞のようにイネの機能を備えた植物体に成長する。
生殖細胞である花粉は、親の遺伝子の半分しか持たない。したがって、花粉の培養によって得られる植物体は半数体になり、子を作ることができない。ところが、培養の過程で自然倍加という現象が起こり、二倍体に成長するものもある。二倍体から得られる種を栽培すると、親と同じ姿のイネに成長する。つまり遺伝的固定が可能になる。これがイネの葯培養のプロセスだ。
イネの葯培養の再生過程には、3つのボトルネックがある。①花粉からカルスになる割合が低い、②カルスからイネになる割合が低い、③再生したイネの中にアルビノが生じる。さらには、アルビノではなく緑色植物に成長したイネのうち自然倍加の二倍体になるのは3割ほど。カルスにならなかった花粉、イネにならなかったカルス、アルビノになったイネ、二倍体にならなかった半数体のイネはすべて栽培できないため廃棄されることになる。

植物育種研究室では、二倍体緑色植物を効率良く再生させるため、これらのボトルネックの解消に取り組んできた。イネの葯培養の効率に関与する要因としては、遺伝子型、ドナー植物の栽培条件、花粉発育時期、葯の前処理、培地組成、培養環境、アルビノ発生などがある。
このうち花粉発育時期については、花粉の発育時期別に培養した葯のカルス形成率を調べた。花粉の発育時期は1核期(前期・中期・後期)、2核期(前期・後期)、3核期があり、1核期の前期・中期はそれぞれ2段階に分けて、A~Hの8段階に区分される。キタアケ、きらら397について、それぞれの段階の花粉を培養したところ、カルス形成率が最も高かったのはC・D期、すなわち1核中期だった。1核前期はほとんどカルスが出来ず、1核後期以降は、1核中期ほどではないものの、ある程度カルスが形成されることが分かった。
培養環境については、培養温度、容器の通気、葯密度、カルスの移植操作について調べた。培養温度では25℃一定よりも昼30℃夜20℃で変温させた方がよく、容器の通気は密閉しない方がよい。また、葯密度については低い方が、カルスの移植操作は、カルスが付着した液体培地を除去した方がよいことがわかった。
岡本准教授は、今後の取組みとして、遺伝子型の研究をあげる。
「イネの品種によりカルスの出来方が異なります。このことはカルスの形成のしやすさに遺伝子が影響していることを示唆しています。そこで葯培養効率を支配している遺伝子を明らかにしたいと考えています。ボトルネックとなっている部分を解消するため培養条件(環境)の改善に取り組んできましたが、それだけでは乗り越えられない部分があると考えられるからです」
新品種育種は、地域の環境に合ったものを選んで作られるため、環境の異なる地域では栽培できない。だが、葯培養の技術は国内外を問わずに利用できる。岡本准教授は、「基礎研究と応用を行き来しながら、葯培養のボトルネックを解消し、まずは北海道のイネ育種にさらに貢献したい。その先には、酪農学園大学の小さなラボで蓄積してきた葯培養効率の改善技術を、道外、海外で葯培養に取り組んでいる技術者に届け、イネ品種改良のスピードアップに貢献できたらいいですね」と語っている。

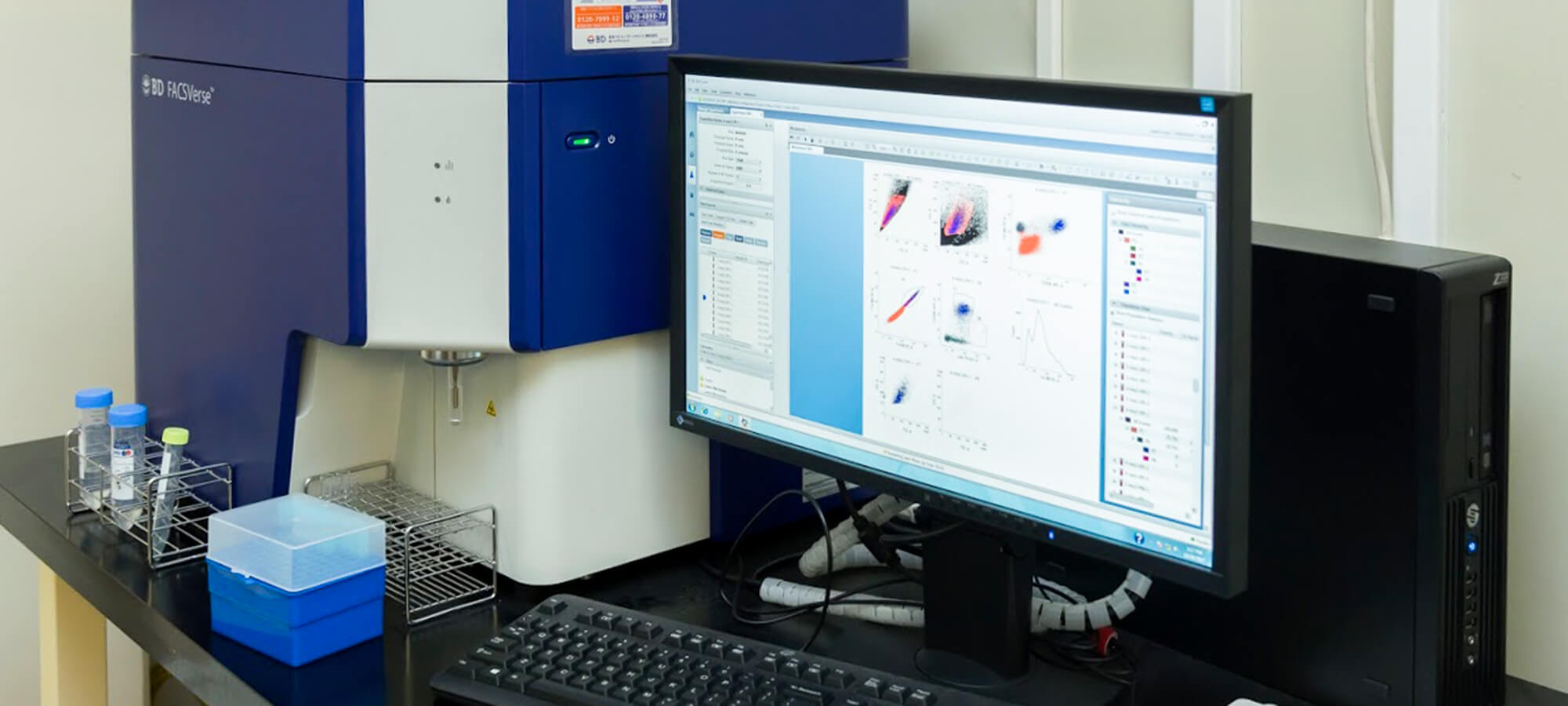
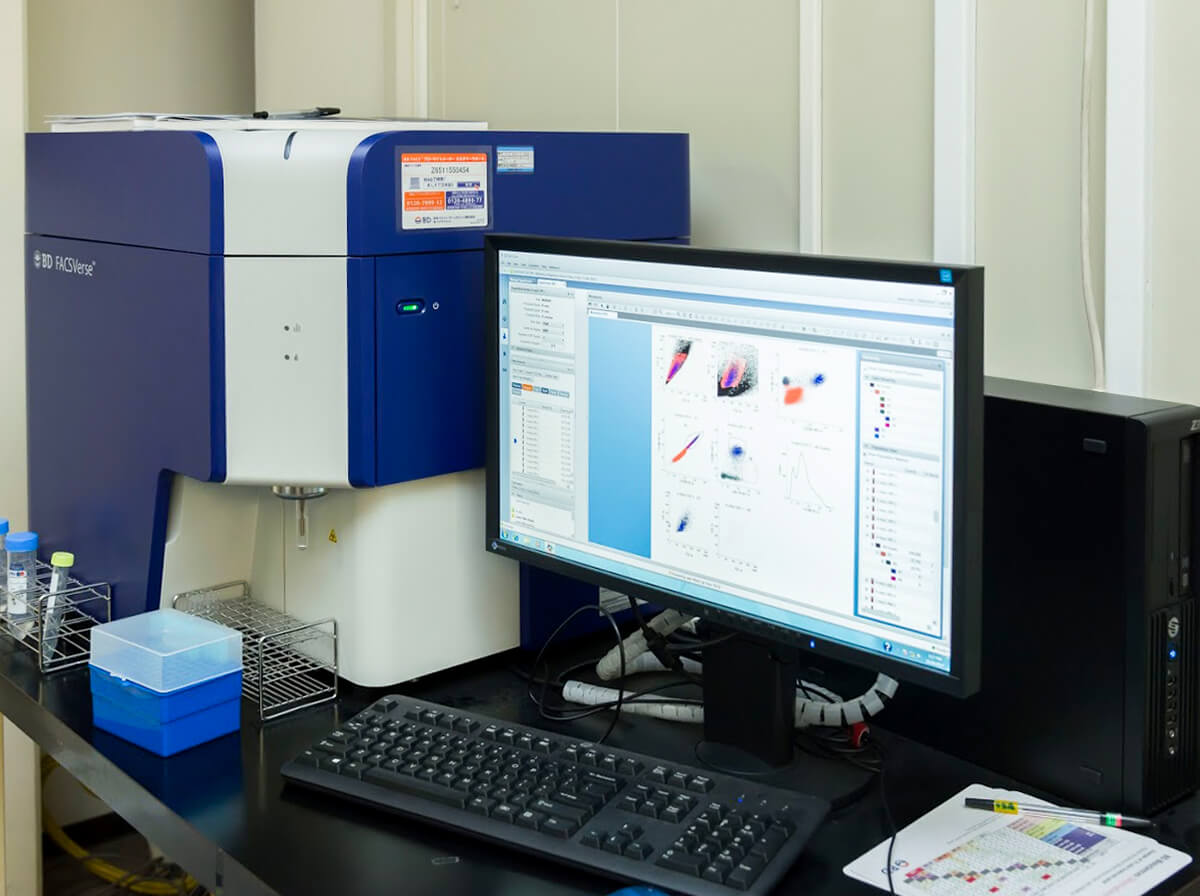


 資料請求
資料請求 受験生サイト
受験生サイト